まずは、何回かに分けて川越線の紹介をしたいと思います。
初回となる今回のテーマは『路線概要』です。
早い話が、総延長や構造等をサクッとまとめてご紹介します。
| 種類 | 普通鉄道(在来線・幹線) |
| 起点 | 大宮駅 |
| 終点 | 高麗川駅 |
| 駅数 | 11 |
| 電略記号 | カハセ |
| 開業年月日 | 1940年(昭和15年) 7月22日 |
| 所有者 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 運営者 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 路線距離 | 30.6 km |
| 軌間 | 1,067 mm |
| 線路数 | 複線(大宮駅-日進駅) 単線(日進駅-高麗川駅) |
| 電化方式 | 直流1,500 V 架空電車線方式 |
| 閉塞方式 | 自動閉塞式(大宮 – 川越間) 特殊自動閉塞式(川越 – 高麗川間 / 軌道回路検知式) |
| 保安装置 | ATS-P |
| 最高速度 | 95 km/h |
| 主な使用車両 | E233系7000番台 (川越車両センター所属 / 10両編成) 東京臨海高速鉄道70-000形 (東臨運輸区所属 / 10両編成) 209系3000番台 (川越車両センター所属 / 4両編成) 209系3100番台 (川越車両センター所属 / 4両編成) 209系3500番台 (川越車両センター所属 / 4両編成) E231系3000番台 (川越車両センター所属 / 4両編成) |
概要だけ列挙すると、このような感じになります。
川越出身の自分的には、「大宮駅から高麗川駅まで30キロ」というのは感覚より長く思えます。
しかし、路線が東西にほぼ真っすぐ走っているため、直線距離と考えれば納得も行く距離です。
国鉄再建法制定時点で既に輸送密度が8000人を超えており、幹線に制定されています。
2005年7月末からは大宮 – 武蔵高萩間でATOSの運用も始まっています。
ほとんどの設備は全線で共通していますが、閉塞方式と運転系統は川越駅を境に異なっています。
川越 – 大宮間では、E233系を中心とした10両編成の電車が使用されています。
川越 – 高麗川間では、209系3000番台等の、半自動ドア対応4両編成の電車が使用されています。
ただし、川越駅以東でも、一部南古谷発の高麗川方面行4両編成の運用が設定されています。
一方、川越駅以西に10両編成の列車が入ることはありません。
と、つらつらと概要を書くとこんな感じになります。
次回は、開業経緯と開業から今日までの歴史について深掘りをしてみたいと思います。

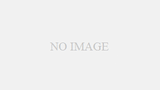
コメント